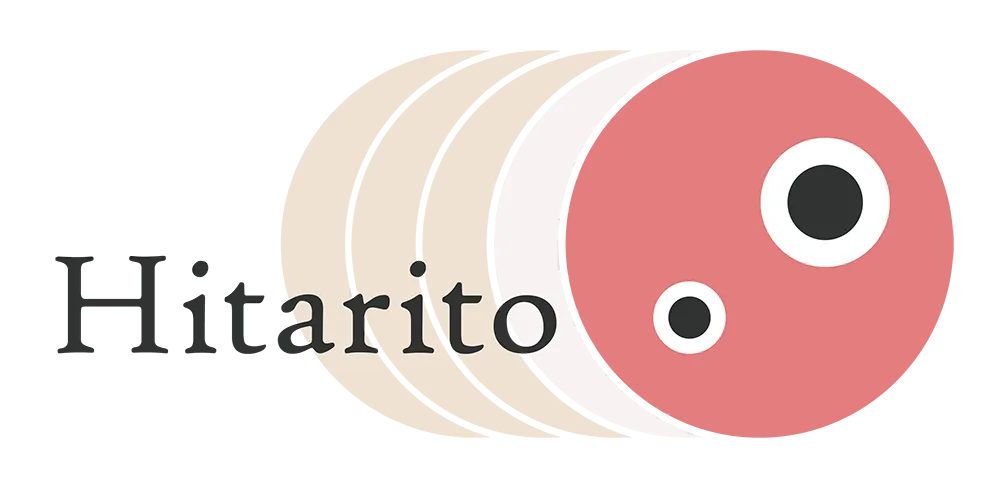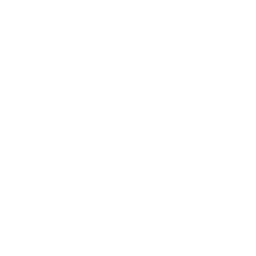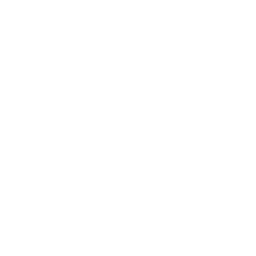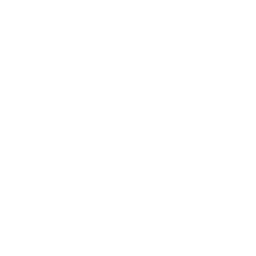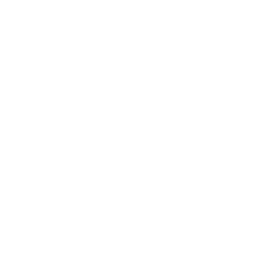お中元とお歳暮の違いは?両方贈るべきか、基礎知識やマナーを解説

お中元とお歳暮は、お世話になった人にギフトを贈る日本の伝統文化です。しかし、2つは何が違うのか、特徴がわからない人も多いでしょう。そこでこの記事では、お中元とお歳暮の概要を解説し、時期や金額などそれぞれの違いやどちらも必要なのか説明します。
この記事を読むための時間:3分
お中元とは?
お中元とは、新年が明けてから「半年間」の感謝の気持ちを伝えるため、夏頃に贈り物をする風習です。基本的には、半年の間でお世話になった上司や親戚、両親、取引先など、自分よりも立場が上の人に向けて贈り物をします。また、近年は感謝の気持ちだけでなく、夏の暑い日でも健康に過ごせるようにという意味合いも含まれています。
お歳暮とは?
お歳暮とは、新年が明けてから「1年間」の感謝の気持ちを伝えるため、年末に贈り物をする風習です。基本的にはお中元と同じく、親戚や上司など自分よりも立場が上の人に向けて贈ります。
お中元とお歳暮の違い
お中元とお歳暮の違いは、以下の5つです。
- 由来
- 贈る時期
- 贈る品物
- 贈り物の金額
- のし紙の表書き
それぞれについて解説します。
由来
お中元の由来は、中国にある「三元の日」だといわれています。三元とは上元・中元・下元という3つの時期を表すもので、その中の「中元」が日本の7月頃にあたるため、お中元の起源ではないかと考えられています。さらに日本には、夏のお盆時期に祖先を供養する風習があり、お盆と中元が結びついて、お世話になった人へ感謝の気持ちやギフトを贈る「お中元」に発展したというのが有力です。
一方、お歳暮の由来は「御霊祭り」という年末年始に先祖を祀る行事だといわれています。祖先へのお供物が時代とともに変化して、身近な人に感謝を伝える文化になり、今のような年末に贈り物をする「お歳暮」に発展したと考えられています。
贈る時期
お中元を贈る時期は、7月上旬から8月中旬の夏頃です。一方、お歳暮を贈るのは12月上旬から12月31日の年末までです。ただし、どちらも時期は地域ごとに変わるため、贈る際は相手の住んでいる土地に合わせる必要があります。
贈る品物
贈る品物は、お中元とお歳暮で明確に決まっているわけではありません。一般的には、お中元は夏頃に贈るものなので、果物やゼリーなどの冷たいものを贈ります。お歳暮は年末にお祝いできるように、お肉や魚介類、お菓子など少し高級なものを贈る場合が多いです。
贈り物の金額
お中元は、新年が明けてから夏までの「半年間」の感謝を伝えるものです。一方、お歳暮は新年が明けてから年末までの「1年間」の感謝を伝えるものなので、期間の長いお歳暮の方が贈り物の金額が高くなります。おおよその目安は、お歳暮の金額がお中元よりも2〜3割程高くなるくらいが望ましいです。ただし、相場は相手によって変わるので、贈り先に失礼にならないようにギフトの金額を決めましょう。
のし紙の表書き
お中元とお歳暮は、どちらも贈り物に「のし紙」をつけます。お中元には「お中元」や「御中元」と表書きをして、お歳暮には「お歳暮」や「御歳暮」の表書きをします。
お中元とお歳暮はどちらも贈る必要がある?
お中元とお歳暮は、どちらも贈るという決まりはありません。片方だけでもマナー違反にはならないので、両方渡すことに重きを置くのではなく、感謝を伝えるのを大切にしましょう。また、片方のみの場合は、年間の気持ちを伝えられるお歳暮を贈るのが望ましいです。
お中元とお歳暮は違いを理解して贈りましょう
お中元とお歳暮は、どちらもお世話になった人にギフトを贈る文化ですが、時期や由来などが異なります。また、基本的には両方贈る場合が多いですが、明確な決まりがあるわけではないので、片方のみでもマナー違反にはなりません。ただし、片方のみ贈る場合は、1年間の感謝を伝えるお歳暮の方がふさわしいです。お中元とお歳暮は、それぞれの違いを理解して贈りましょう。