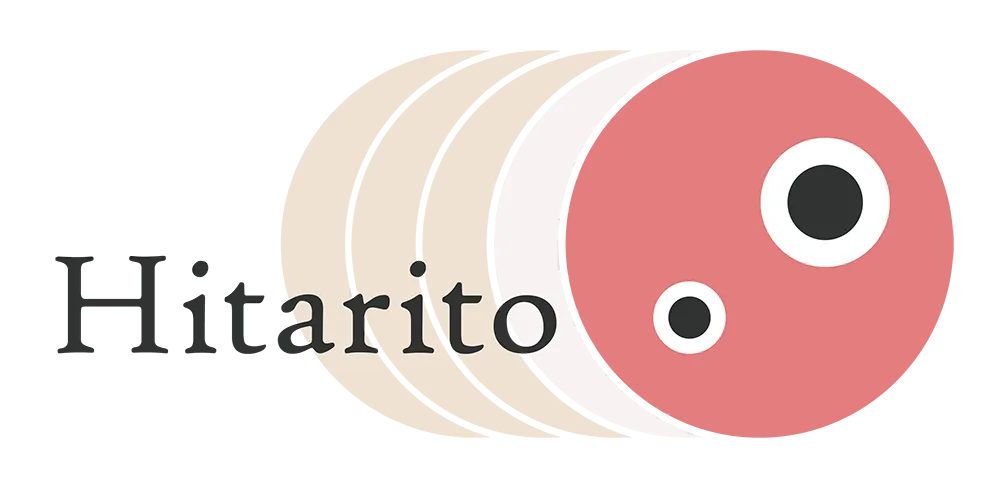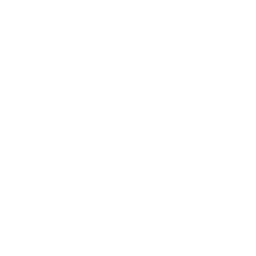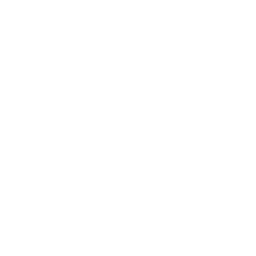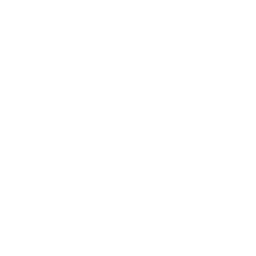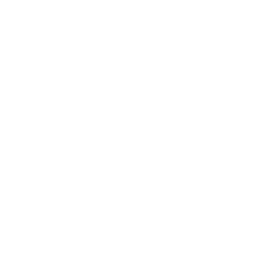お中元のマナーとは?基礎知識や贈る際に気をつけることを解説

お世話になった人には、夏頃にお中元を贈って感謝の気持ちを伝えます。しかし、年に一度のことなので、適切なマナーや贈る際の注意点がわからない人もいるでしょう。そこでこの記事では、お中元のマナーについて、贈る側ともらう側の両方を解説します。
この記事を読むための時間:3分
お中元とは
お中元とは、お世話になった人や繋がりの深い人に、日頃の感謝の気持ちを伝えるため夏頃に贈り物をする文化です。時期は7月初旬から8月中旬までといわれており、夏場に贈るため、ギフトはゼリーやジュースなど冷たいものが人気です。
お中元を贈る際のマナー
お中元を贈る際のマナーは、以下の5つです。
- 事前連絡と送り状を送る
- 基本は手渡しにする
- 地域ごとの時期に合わせて贈る
- 金額は相場の範囲内にする
- お中元用の熨斗(のし)を使う
それぞれについて解説します。
事前連絡と送り状を送る
お中元を手渡しする場合は、急に訪問すると迷惑になるので、事前にお中元を渡す旨を連絡します。また、郵送で贈る場合は送り状を送付して、お中元が届くというのを相手に知らせます。
基本は手渡しにする
本来お中元は、直接手渡しするのがマナーです。しかし、近年は遠方に住んでいたり、訪問する日程が合わなかったりする場合もあるため、郵送で贈るのでも問題ありません。もし会えるのであれば直接ギフトを贈り、相手への感謝の気持ちを伝えると想いが伝わりやすいでしょう。
地域ごとの時期に合わせて贈る
お中元を贈る時期は、7月初旬〜8月中旬までですが、地域によっても差があります。関東では7月初旬から7月15日頃までですが、関西では7月下旬〜8月15日頃までといわれています。そのため、贈る相手の住んでいる地域に合わせて、贈る時期を考えましょう。
金額は相場の範囲内にする
お中元の金額は、贈る相手によって以下の相場があります。
- 両親や親戚:3〜5千円
- 上司や取引先:3千〜1万円
基本的には、近しい間柄の人は気軽に渡せる金額のものを贈ります。上司や取引先のように、仕事で特にお世話になった相手には、感謝の気持ちを込めて少し金額が高くなっても大丈夫です。ただし、お中元は毎年贈るもので前年より安価なものを贈るのは失礼になるため、続けられる金額のものを選ぶのが大切です。
お中元用の熨斗(のし)を使う
お中元には、熨斗(のし)をつけるのがマナーです。種類は紅白カラーの水引を蝶結びにした、お祝い用のものが望ましいです。また、本来は手渡しをするものなので包装の上から熨斗をつける「外のし」になりますが、郵送の場合は配送時に破れる可能性があるため、包装の中に熨斗をつける「内のし」にします。熨斗には「お中元」と表書きをして、何が届いたか相手にわかるようにしましょう。
お中元をもらう側のマナー
お中元をもらう側のマナーは、以下の2つです。
- すぐにお礼状を送る
- 相手に合わせてお返しを用意する
それぞれについて解説します。
すぐにお礼状を送る
お中元をもらったら、すぐにお礼状を送りましょう。おおよその目安は、ギフトを受け取ってから3日以内に郵送をして、1週間以内には相手に届くようにします。近年は電話でお礼を伝えるだけの場合もありますが、立場が上の相手や仕事の関係者には、失礼にならないようマナーを守ってお礼状を送るのが大切です。
相手に合わせてお返しを用意する
お中元をもらったら、相手に合わせてお返しを用意します。お返しは必ずするものではないので、自分との関係性や今後の繋がりなどを考慮して贈るか決めましょう。お返しする場合は、受け取ったものより高価なものを贈るのは失礼になるため、同じくらいの金額のものを選ぶのがマナーです。
お中元はマナーを守って贈りましょう
お中元を贈る際は、事前連絡や送り状を送ったり、相手の地域に合わせて時期を決めたりとマナーがあります。また、もらう側にも受け取った際の対応に決まりがあるので、お中元のやり取りをする際は事前にマナーを確認しましょう。