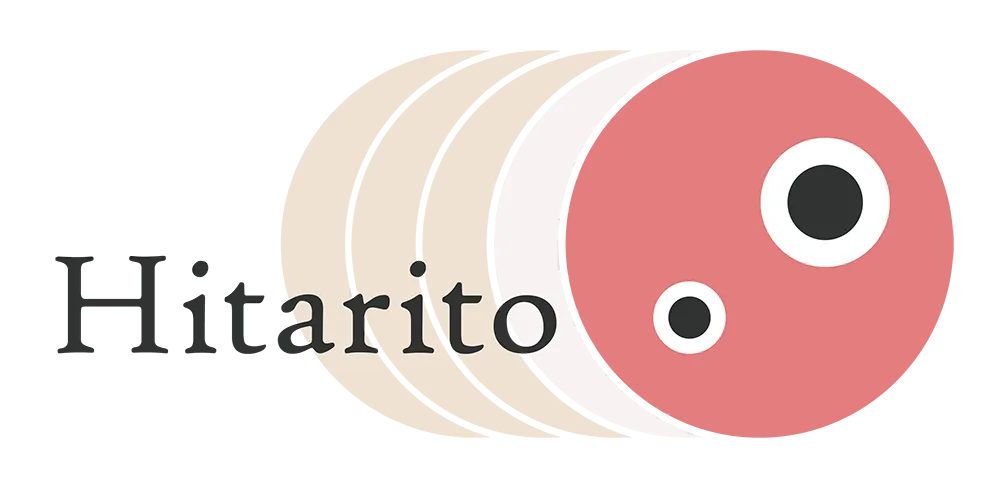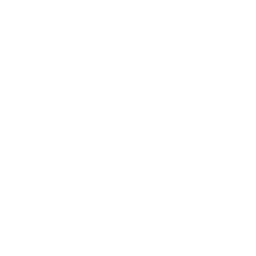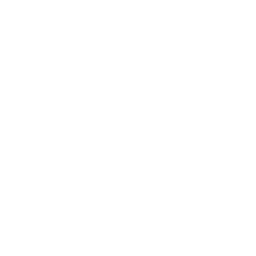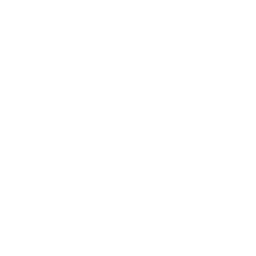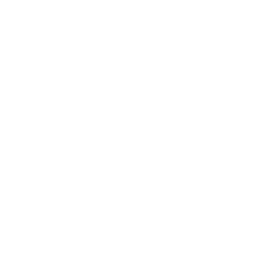お歳暮のお返し時期はいつまで?金額やお礼状などのマナーを解説

1年間お世話になった人には、お歳暮という形で年末に贈り物をして感謝の気持ちを伝えます。しかし、今までやり取りのなかった人からギフトをいただいた時はお返しをするべきなのか、マナーがわからない場合もあるでしょう。そこでこの記事では、お歳暮のお返しは必要か、贈る時期やマナーを解説します。
この記事を読むための時間:3分
お歳暮をもらったらお返しは必要?
お歳暮をもらったら、必ずお返しをするわけではありません。近年はお礼の気持ちを込めてお返しする人も多いですが、お礼状のみでもマナー違反にはならないです。また、お返しの品物を贈ると来年からもお歳暮を贈るという意味に受け取られるので、今後のやり取りを控える場合は贈らない人もいます。
お歳暮のお返しをする時期
お歳暮のお返しは、すぐに贈ると相手に気を遣わせるため、1週間程度期間を空けるのが望ましいです。一般的には、年が明けてから1月7日の松の内までに「御年賀」として贈る場合が多く、過ぎる場合は2月4日の立春までに「寒中見舞い」として贈っても問題ありません。
お歳暮のお返しをする際のマナー
お歳暮のお返しをする際のマナーは、以下の5つです。
- お礼状を送る
- 遅れる場合は連絡をする
- のし紙は時期に合わせる
- 金額は相場の範囲内にする
- お返ししたら来年はお歳暮を贈る
それぞれについて解説します。
お礼状を送る
お歳暮を受け取ったら、お返しをするしないに関わらず、すぐにお礼状を送りましょう。近年は電話やメッセージのみでお礼を伝える人も多いですが、本来は感謝の気持ちを書いたお礼状を送るのがマナーです。また、もしもお返しの品物を贈らない、来年からのお歳暮のやり取りをしないなどの場合は「来年からのお気遣いは結構です」など失礼にならないようお礼状に書き添えます。
遅れる場合は連絡をする
お歳暮のお返しを贈るのは、年が明けて1月7日の松の内の頃までが一般的なので、もしも遅れる場合は事前に連絡をしましょう。電話やメッセージで連絡をすると、相手にも安心感を与えて失礼になりません。
のし紙は時期に合わせる
お返しの品物につけるのし紙は、贈る時期に合わせましょう。年明けの松の内までに贈る場合は、のし紙に「御年賀」と表書きをします。間に合わない場合は、立春までなら「寒中見舞い」になります。間違えると相手によっては「マナーがなっていない」と受け取られるので、時期に合わせて書くのが大切です。
金額は相場の範囲内にする
お返しの品物の金額は、相場の範囲内にしましょう。おおよその相場は、いただいた贈り物の半額から同額といわれており、あまりにも高価なものを贈ると失礼になります。そのため、お歳暮をいただいたら大体の金額を確認して、高額になり過ぎないお返しを選ぶのが大切です。
お返ししたら来年はお歳暮を贈る
いただいたお歳暮に対して品物でお返しをするのは、来年以降もお歳暮を贈り合うという意味に受け取られる場合が多いです。そのため、お返しをしたら来年はこちらからお歳暮の準備をしましょう。もしも今回限りにしたい場合は、お礼状や電話などでそれとなく相手に伝える必要があります。
お歳暮のお返しは時期やマナーを守りましょう
お歳暮をもらったら、必ずしもお返しをするわけではありません。近年はお礼のためお返しをする人も多いですが、感謝の気持ちを書いたお礼状だけでもマナー違反にはならないです。もしもお返しをする場合は、贈る時期やのし紙の表書き、品物の金額などには気をつけて失礼にならないようにするのが大切です。
またお返しの品物を贈るのは、来年以降もお歳暮のやり取りをするという意味になるので、翌年以降は自分からお歳暮の用意をします。お歳暮のお返しはマナーを守って贈りましょう。