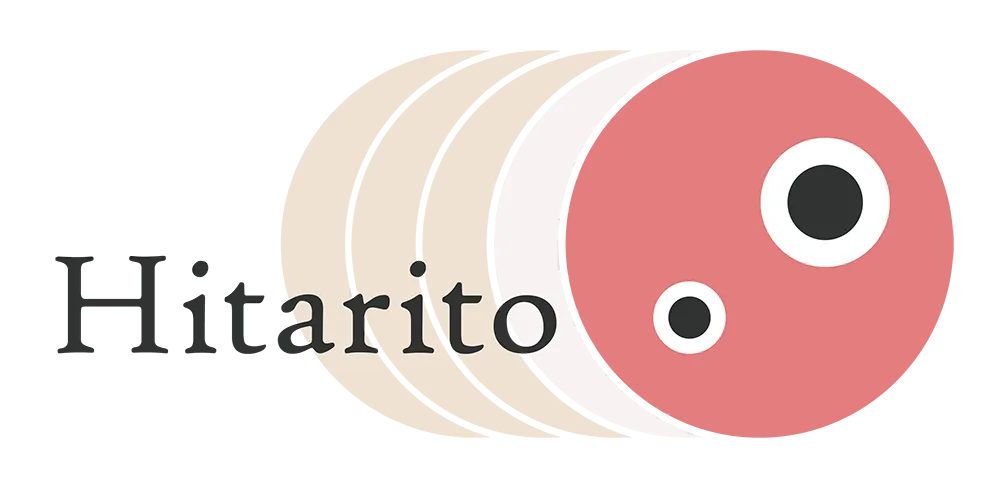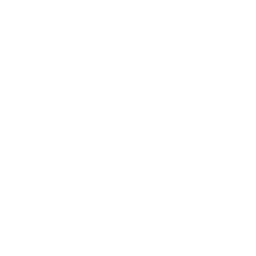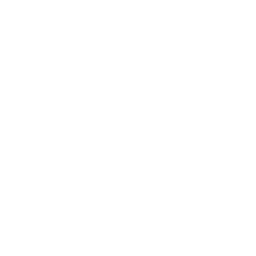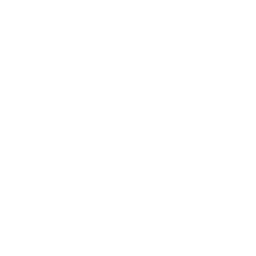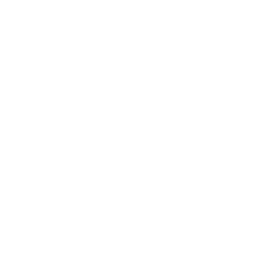お歳暮は誰に贈るもの?上司や両親、親戚などの相手別に贈り方を解説

お歳暮は、1年間の感謝の気持ちを込めて年末に贈るギフトです。しかし、どのくらい親しい人に贈るものなのか、相手を決める基準がわからないこともあるでしょう。そこでこの記事では、お歳暮は誰に贈るものか解説し、相手別の贈り方や受け取りができない相手についても紹介します。
この記事を読むための時間:3分
お歳暮は誰に贈るもの?
お歳暮は1年間の感謝の気持ちを伝えるために、お世話になった人や繋がりの深い人に贈るものです。そのため、日頃のお礼を伝えたい相手がいる場合は、お歳暮を贈るとお互いに良い関係性が築けるでしょう。一般的には、両親や親戚などの身内、上司や取引先などの会社関係者、友人や仲人などの親しい人に贈る場合が多いです。
相手別のお歳暮の贈り方
お歳暮の贈り方を、以下の5つの相手別に解説します。
- 両親・親戚
- 会社関係者
- 仲人
- 友人
- 習い事の先生
両親・親戚
両親や親戚などの身内にお歳暮を贈る場合は、相手の好みを考えて、もらって嬉しいものを選ぶのが大切です。また、贈る際はなるべく直接手渡しをして、品物だけでなく感謝の気持ちを伝えると喜ばれます。手渡しできない場合は、手紙を添える・電話をするなどして相手に想いが伝わるようにしましょう。
会社関係者
上司や同僚、取引先などの会社関係者に贈る場合は、自分が勤めている職場のルールに従うのが大切です。会社によってはお歳暮のやり取りを禁止しているところや、贈る品物の金額などに決まりを設けているところもあるので、事前に確認しなくてはなりません。会社でのトラブルを防ぐためにも、ルールには必ず従いましょう。
仲人
結婚式を挙げてから3年間は、仲人にお歳暮を贈るのがマナーです。贈り物を選ぶ時は、相手の年齢や好みに合わせると喜ばれるでしょう。また、3年を過ぎた後も親しい関係が続いている場合は、それ以降もお歳暮を贈って大丈夫です。
友人
親しい友人にお歳暮を贈る場合は、風習や文化などのマナーを守るよりも、相手に喜んでもらうのが大切です。贈り物は相手の好みのものを選んで、気を遣わせないように、高価すぎないものを贈るのが望ましいです。気軽に贈れる品物なら、相手も気負わずに受け取ってくれて、お歳暮のやり取りを続けやすいでしょう。
習い事の先生
近年はあまり見かけませんが、日本では古くから子どもや自分の習い事の先生にお歳暮を贈る風習があります。そのため、お稽古事の先生にも感謝の気持ちや翌年への挨拶の意味を込めて、お歳暮を贈っても問題ありません。ただし、現在は習い事の先生も会社員である場合が多く、規約上受け取れなかったり、お歳暮のやり取りをしないと決めていたりすることもあるため、事前に贈れるか確認する必要があります。
お歳暮を贈れない相手について
お歳暮はお世話になった人に贈るものですが、中には受け取りができない相手もいます。政治家や義務教育の先生など、国の仕事に従事している人は、基本的にはお歳暮を受け取ることができません。贈ると賄賂や汚職につながる可能性があり、そもそもギフトのやり取り自体が禁止されています。そのため、贈る相手には気をつけて、贈れない時は直接お礼を言うなど別な方法で感謝の気持ちを伝えましょう。
お歳暮は感謝を伝えたい人に贈りましょう
お歳暮は、日頃からお世話になっている人に贈るものです。一般的には両親や親戚、上司、友人、仲人に贈る場合が多く、感謝を伝えたい相手なら誰に贈っても問題ありません。ただし、政治家や義務教育の先生など、国の仕事に従事している人の中には、お歳暮の受け取りが禁止されている人もいます。
そのため、贈る場合は事前に贈っても良いか確認をして、無理な場合は直接お礼を言うなどして感謝の気持ちを伝えましょう。