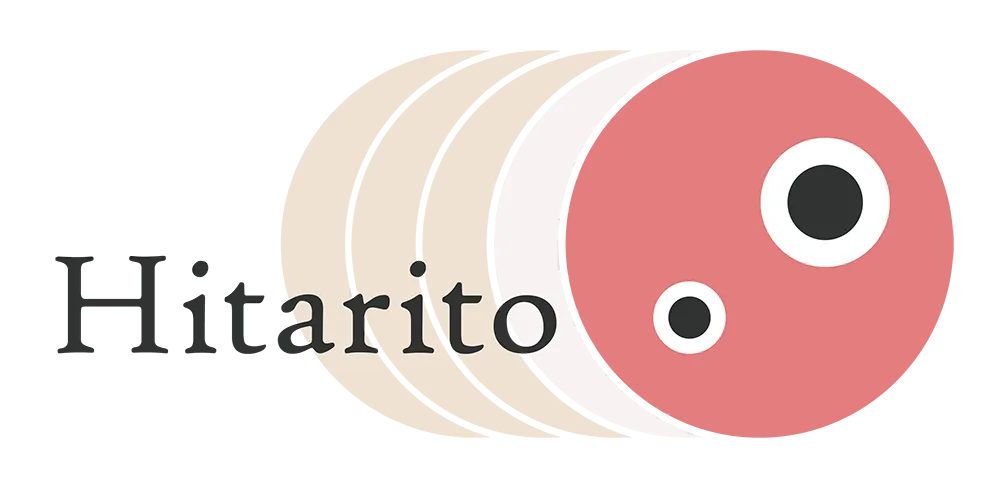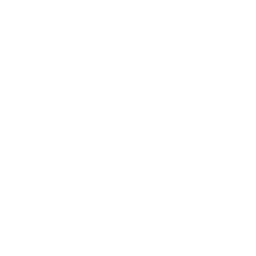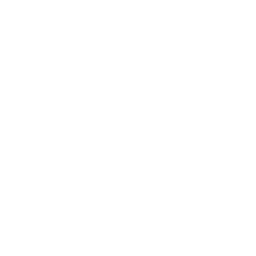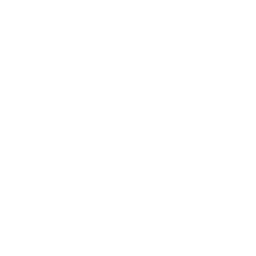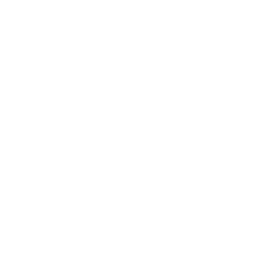お歳暮を贈る時期はいつからいつまで?期間に遅れた時の対処法も解説

お歳暮はお世話になった人への感謝の気持ちを込めて、年末に届ける贈り物です。しかし、年末とは具体的に何日を指すのか、時期がわからない人もいるでしょう。そこでこの記事では、お歳暮を贈る時期や準備を始めるタイミング、期間に遅れた時の対処法を解説します。
この記事を読むための時間:3分
お歳暮を贈る時期について
お歳暮を贈る時期について、以下の4つより解説します。
- 正式な時期
- 関東圏
- 関西圏
- その他の地域
正式な時期
お歳暮は、日頃からお世話になっている人に1年間の感謝の気持ちを込めて贈るものなので、12月の年末に贈ります。本来はお正月を始める12月13日の「事始め」の時期に贈るとされていましたが、現代は仕事などで忙しい場合も多く、12月31日までに贈るのが一般的です。
関東圏
お歳暮を贈る時期は、地域によって差があります。関東圏では、12月上旬から12月20日前後に贈るのが一般的で、関西圏やその他の地域と異なります。贈る際は、相手の住んでいる地域に合わせましょう。
関西圏
関西圏では、12月13日から12月20日までにお歳暮を贈るのが一般的です。他の地域よりも期間が短いため、関西圏に贈り先がある場合は、余裕を持って準備を始めましょう。
その他の地域
関東・関西以外の地域では、12月初旬から12月25日までにお歳暮を贈るのが一般的です。ただし、12月は年末で忙しいこともあり、近年は11月頃に贈る家庭も増えています。
お歳暮の準備を始めるタイミング
お歳暮の準備は、贈る日の2ヶ月前頃に始めて、1ヶ月前までには全ての手配を終えるのが望ましいです。12月中に届けるのであれば、11月には手配を済ませておくと、遅れることなく相手に贈れます。
あまりにもギリギリの日程で用意をすると、配送予約が埋まっていたり、贈りたいギフトが品切れになっていたりするので、余裕を持って準備を始めると安心です。スムーズに手配を進めるためにも、早めにカタログやネットなどを見て、贈るギフトを考えましょう。
お歳暮を贈る時期が遅れた時の対処法
お歳暮を贈るのが間に合わない時は、まず相手に遅れることを伝えてお詫びしましょう。遅れる場合は以下のように贈るのが適切です。
- 年明けに「御年賀」として贈る
- 「寒中見舞い」として贈る
年明けに「御年賀」として贈る
お歳暮を贈るのに遅れた時は、年が明けてから「御年賀」として贈れます。御年賀とは新年の挨拶を込めて贈るもので、この場合は配送ではなく手渡しが望ましいとされています。時期は関東圏では1月7日まで、それ以外の地域では1月15日までとなり、地域ごとに差があるため注意が必要です。また、贈り物ののし紙は、表書きを「御年賀」に変えるのを忘れずに行いましょう。
「寒中見舞い」として贈る
お歳暮と御年賀に間に合わない時は「寒中見舞い」として贈る方法もあります。寒中見舞いは、御年賀が終わる時期(関東では1月7日、それ以外では1月15日)から2月4日の立春頃までに、相手への敬意を払う意味合いで贈るものです。贈る際は、御年賀と同じくのし紙の表書きを「寒中見舞い」に変えましょう。
お歳暮は余裕をもって準備しましょう
お歳暮は、お正月を始める12月13日の「事始め」に贈るのが正式な時期だといわれています。しかし近年は、年末に忙しいということもあり、12月31日までに贈るのが一般的です。ただし、関東圏では12月上旬から12月20日前後まで、関西圏では12月13日から12月20日前後までに贈る風習があり、相手の住んでいる地域に合わせるのが大切です。
また、遅れる場合は相手にお詫びの連絡をして、年が明けてから「御年賀」や「寒中見舞い」に変えて贈ります。遅れないためにも余裕を持って準備を始めましょう。